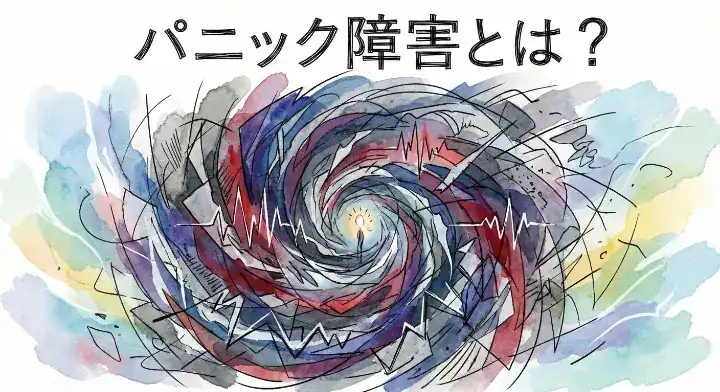パニック障害はどんな病気ですか?
パニック障害は、突然の強い不安を伴う動悸やめまい、息が詰まる、嘔気、手足のふるえなどの「パニック発作」を起こし、それが原因で生活に支障が出ている状態をパニック障害と言います。パニック障害は決して珍しい病気ではなく、日本では成人の1~2%が経験すると言われており、20~40代での発症が多い傾向があります。また、男性よりも女性に発症しやすいとされています。
最初に発作が起こると、不安感が強まり、不安感のループが形成されます。初期の段階で適切な治療を受けることで、症状をコントロールすることが可能です。特に、上手にお薬を使うことで、不安感のループを断ち切る事が大事です。
心理的ストレスもきっかけになりますが、寝不足等含め体調のコンディションが悪い時にも出現する事があります。
パニック障害でよくみられる症状は?
パニック発作
パニック障害の最も特徴的な症状は、パニック発作です。パニック発作は初期から見られる症状で、予期せず繰り返されることが特徴的です。パニック発作は予期できませんので、通学中に突然起こったり、寝ている間に起こったりすることもあります。
パニック発作は、突然かつ明確な原因なく発生します。発作中には以下のような身体的、感情的症状が現れることがあります。
- 心拍数の増加
- 恐怖感
- 胸の痛みや圧迫感
- 息苦しさや窒息感
- めまいやふらつき
- 冷や汗、震え、または熱感
予期不安
パニック発作は予期できませんし、繰り返すため、「このままでは死んでしまう」「また発作が起きてしまう」と考えるようになります。この「パニック発作が起こるかもしれない」という不安感を予期不安と言います。
広場恐怖
広場恐怖とは、特定の場所や状況で「パニック発作が起きるかもしれない」という不安から、その場所を避けるようになる症状です。
「広場」という名前ですが、公園のような開けた場所だけを指すわけではありません。電車やバスの中、スーパー、ジム、映画館など、人によって苦手な場所はさまざまです。
症状が進むと、外出そのものが難しくなり、家に引きこもりがちになってしまうこともあります。パニック障害と併せて発症するケースが非常に多いのが特徴です。
これらの症状以外にも、予期不安や広場恐怖が強くなり、抑うつ状態になることもあります。
パニック障害の診断方法は?
パニック障害の診断は、医師が患者の症状や病歴を詳細に聞き取り、他の医学的原因が重なっていないかどうか調べる事から始まります。心臓病や甲状腺異常など、似た症状を引き起こす他の病気がないかを確認するために、血液検査や心電図などが行われることもあります。
パニック障害の治療にはどんな選択肢がありますか?
パニック障害の治療の目的は、パニック発作を起こさないこと、そして予期不安や広場恐怖があれば軽減させることです。この目的のために薬物療法や精神療法を行います。
薬物療法
パニック障害に対してよく使われる薬剤は、選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)や抗不安薬です。これら薬剤の効果は人によって違うので、効果を確認しながら量や内服回数を調整します。薬物療法を望んでない方は、当院以外のカウンセリングを有する医療機関にご相談下さい。
精神療法
パニック障害では、薬物療法に加えて精神療法を行うことが重要です。特に、認知行動療法や曝露療法などが有効とされています。認知行動療法は、何か出来事に対して悲観的に物事を考えてしまう癖を改善し、パニック障害を悪化させる思考を断つ方法です。一方で、曝露療法は広場恐怖を引き起こす場所に対して、あえて直面することで、不安や恐怖感に徐々に慣れてもらうことで軽減する方法です。基本的には薬物療法をお勧めしますが、薬物療法をお望みでない方は、当院以外のカウンセリングを有する医療機関にご相談しても良いかもしれません。
パニック障害になったら気をつけることはありますか?
日常生活でストレスを管理し、規則正しい生活を心がけることも重要です。適度な運動、健康的な食事、十分な睡眠が推奨されます。また、アルコールやカフェインの摂取を控えることも、症状の悪化を防ぐために役立ちます。
パニック障害に関するよくあるご質問
Q1. パニック発作は命に関わりますか?
A1. 多くの場合、パニック発作自体は命に関わるものではありませんが、強い動悸や息苦しさ、胸の圧迫感が続くため、心臓病などとの区別が重要です。医療機関での評価をおすすめします。
Q2. パニック障害は自然に治りますか?
A2. 一時的に症状が軽くなることはありますが、放置すると再発や悪化の可能性があります。薬物療法や認知行動療法など、適切な治療で改善を目指すことが大切です。
Q3. 発作が起きたときの対処法はありますか?
A3. 深呼吸や意識的なリラックスで症状を和らげることがありますが、根本改善には治療が必要です。当院では症状に合わせた対処法も併せてご案内します。
文責 院長(医学博士、日本専門医機構認定精神科専門医、精神保健指定医)
参考記事